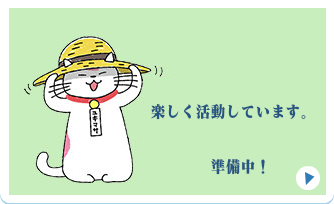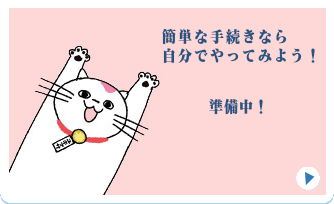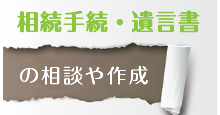

![]()
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

![]()
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
平成29年5月29日、「法定相続情報証明制度」が開始されました。
詳細は、別コーナーにて説明しています。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

![]()
相続の手続きは、以下のような流れで進行していきます。
遺産の分割だけでなく、確定申告や納税、その他事務手続きまで幅広い手続きが必要となります。
とりあえず、以下のようなおおまかな流れを把握していただければと思います。

![]()

![]()
この手続きには特に期限はありません。ただ1点だけ、相続放棄に関する手続きだけは原則として人が亡くなってから3カ月以内に行う必要があります。
そのため、その判断をする前提となる相続人の調査、相続財産の調査と評価もそれまでにはおおむね終了させておく必要があります。
相続財産の調査は非常に時間がかかる場合がありますので、注意して下さい。

![]()
亡くなった人が自営業者の場合など給与所得以外の収入がある場合は、亡くなった日から4カ月以内に「準確定申告」が必要となることがあります。
相続税の納税は原則として、亡くなった日から10カ月以内に、現金一括で払う必要があります。
もしそれまでに遺産分割の話がまとまっていない場合は、法定相続分で相続したものとみなして納税しなければなりません。
その後話がまとまってみると相続税額が間違っていたという場合は、税務署にその旨を申告して調整することになります。

![]()
図(*)に挙げた手続きは特にお金に関係しそうなものだけです。
公的保険(社会保障)の手続きは亡くなってから10日や14日以内に するよう求められるものが多いので注意して確認して下さい。
私的保険(生命保険など)の期限は3年や5年といったものが多いですが、契約内容を早目に確認して問い合わせなどを行うとよいでしょう。
それ以外にも免許所やパスポートの返却、各種クレジットカードの手続き、水道光熱費、電話代、インターネット費用の名義変更、各種会員証の処理など多数の手続きがあります。